翌日、蓮は七条の伊緒理の邸を訪ねた。供はもちろん曜である。
師走の冷たく乾き切った空気の中、鼻の頭を赤くして蓮は庇の間に入ると、そこには伊緒理が立って待っていてくれた。
「寒いところをよく来てくれたね。さぁ、中に入って」
伊緒理は蓮の手を取って隣の部屋に連れて行った。
「こんなに冷たくなって」
蓮の右手を両手で挟みこすって温めてくれた。
外の寒さを思って部屋の中は炭櫃が置かれて温められており、蓮はすぐに冷えた体を温められた。しかし、部屋の暖かさよりも、伊緒理の肌に包まれたほうがよほど暖かかった。
伊緒理はすぐに奥の部屋に誘い、お互いの衣服を脱がせ合って褥の上で抱き合った。
「火事が起こった日。大王の近くに侍っていて、火事の喧騒など聞こえなかったので遅れて王宮のそばで火事が起こっていることを知った。大王の寝所までは火が来ないという話であったが、安心はできない。王宮では火の粉が大きな炎にならないように総出で屋根に水をかけていた。その頃あなたが有馬王子の後宮にいるとは知らず、火事に巻き込まれたと聞いて驚いた。無事と聞いて一旦は安心したが、怪我はしていなかったか、怖い思いをしていなかったかと気がかりだった。昨日あなたの顔を見て、やっと安心できたよ」
「ええ、火事と聞いて怪我人がいないかと近寄ってしまったの。だけど、無事に逃げられたわ。伊緒理には心配を掛けてしまって申し訳ありません」
「あなたが無事でよかった」
伊緒理は心の底から絞り出したようなため息をついて、腕の中の蓮を押し倒してその胸に唇を押し当てた。
「あなたは優しい人だから、人を助けようと危険を顧みずに行ってしまったのだろうが、これからは危ないことに近づいてはだめだ。どうか、それだけはわかっておくれよ。私はあなたがいなくなるなんて考えられないんだよ」
と耳元で囁いた。
蓮にとってその言葉は涙が出るほどの嬉しい言葉だった。
「ええ、危ないことに近づかないわ。私も伊緒理と離れてしまうなんて考えられないもの」
と返事して、伊緒理の背中に腕を回した。
それが合図のように、伊緒理は蓮に回していた右手を蓮の頬に当てて、蓮の顔を逃さないようにして唇を重ねた。
優しく触れたが、蓮は自分から伊緒理の唇を吸った。伊緒理がさらに吸い返して、その合間に息をした。
部屋の中では二人の息つかいだけがする。
「……あっ……」
背中から回されていた伊緒理の手は蓮の腹の上からすっと下がって、蓮の足の間へと入った。伊緒理の指が奥に深く入ったので思わず蓮は声を上げた。
「随分と久しぶりだ。あなたの温かくて柔らかい肌が欲しかった」
と言って、肩にくちづけた。
「私もよ……私も」
伊緒理は体を起こして、蓮を下にして見下ろした。蓮は自ら足を開いて、伊緒理の腿の外側に足を置いた。伊緒理は蓮の腰を引き寄せて、自分自身も蓮の足の間に腰を入れた。
蓮は伊緒理と一つになると快感で内側から震えが来て、手を伸ばした。伊緒理に手を握って欲しくなったのだ。
伊緒理は腰を動かしながら、蓮の手を握って、一旦離し、指先を合わせてからすっと指と指の間に自分の指を入れて強く握った。
「ん……あっ……ん」
蓮は伊緒理の強い動きに、抑えようと思っても声が漏れた。
伊緒理との激しい性交の後、蓮は目を瞑ってその余韻に浸った。
伊緒理の愛に満たされると、それまでの自分の波立った心の揺れが嘘のように収まった。
そこへ、伊緒理が話し始めた。
「……蓮……私には夢がある。それは去様のように自分の土地に屋敷を構えて、薬草の研究をしながら身近な人々の病気を治すことだ。そんな活動をしたいと思っている。だから、師である去様のところに定期的に訪れて勉強させてもらっていた……」
蓮は自分の背後から体に回された伊緒理の手を握って、伊緒理の言葉の相槌とした。
「この邸は私の祖母のものだった……。祖母が私に譲ってくれたのだ。祖母が私に残してくれたものはこの屋敷のほかに、都の外に小さな領地があるんだ……。仕事が落ち着けば、典薬寮を辞めて、去様のように私の束蕗原を作りたいと考えている。その時あなたは私の隣にいて欲しい。あなたと一緒に束蕗原のような場所を作りたい」
と、伊緒理は言った。
伊緒理の仕事が落ち着くと言うことは……それはすなわち、大王の命の灯火が消えた後ということになる。
直接的な言葉を使おうものなら、不敬を告発されかねない。蓮は伊緒理が言わんとすることを読み取った。
伊緒理は大后、皇太后の次に近くで大王のご様子を見ている医師団の一人だ。決して蓮に話すことはないが、陰の噂では大王はいつその命が尽きてもおかしくないほど体は弱っているとのこと。
伊緒理がこんな夢を語るのは、そう遠くない日にその夢に向かって踏み出す日が近いと言うことだろうか。
そうだとしても、蓮は伊緒理の夢に心を寄せるのだった。なんと素晴らしい夢だろうか。
「ええ。私は伊緒理のそばにいます。ずっと。あなたがあっちに行けと言ってもいますからね」
と蓮は笑いを含んだ声で言った。
「うん。そんなこと言うもんか。あなたを離さないよ」
伊緒理は後ろから回している蓮を抱く腕に力を込めた。
「……去様のような立派な邸をすぐには構えられるわけではない。屋敷は小さく、使用人も多くない。苦労をかけるはずだ」
「ええ、平気よ。去様のところで見習いの女人たちと一緒に寝起きし、食事の支度の手伝いだってしていたわ。家事は何もできないわけじゃないのよ」
「ふふふ。頼もしいね。あなたと睦まじく暮らせる日が楽しみだ。こんなことを言ってはいけないが、その日が来るのが待ち遠しい」
「……ええ」
蓮は返事をして、後ろの伊緒理に体の向きを変え、その胸の中に潜り込んだ。
「私もよ」
伊緒理も蓮を抱きしめ、髪に口付けした時、庇の間の入り口近くから声がした。
「伊緒理様」
蓮といる時はいつも侍女たちが声をかけるものだが、今は男の声だった。
小さな声だったが、伊緒理にも蓮にもよく聞こえた。
「恒貞(つねさだ)か………」
伊緒理がつぶやいた。恒貞というのはこの邸の家政を見ている重鎮の男である。蓮といる時は高海という若い従者が出てきて世話をしてくれているのだが、今は恒貞が来た。
奥の部屋で二人が何をしているのか想像はついているだろうが、それを遮ってでも伊緒理を呼ぶのは何事が起こったのだろうか。
伊緒理は立ち上がって上着を羽織り、帯を一巻きして結んで几帳を超えて庇の間に行った。
微かにだが伊緒理と男の話し声が途切れ途切れ聞こえてくる。
蓮も起き上がって、下着を身につけ終わったところで伊緒理が戻ってきた。
その顔は表情なく、蓮は怪訝に思って尋ねた。
「どうしたの?」
伊緒理は蓮の前に座り、蓮の両頬に手を掛けて自ら右耳に口を寄せると囁いた。
「………嘘」
蓮は言葉を聞いて、思わず伊緒理の袖を掴んだ。
伊緒理が蓮に行った事実は……
大王崩御。
深更、大王はその命が尽きた。昼間は咳をして苦しんだが、次第に咳は落ち着き、大后と娘の王女に両手を握られている中、静かに息を引き取った。
大王絶命の事実の前に、大后、皇太后の顔は色を無くした。娘の王女だけがすすり泣いて、その声が部屋に響いた。
夜明けまではこのまま、との大后の意向で、侍っていた医師や身近に仕える役人たちは別室で同じように夜明けを待った。
それから重臣たちの元にも伝令が送られ、大王が亡くなられたことは王宮の外に伝わった。
しかし、王宮には様々な目が張り巡らされていて、大后は夜明けを待てと言ったが、大王崩御の知らせは夜明けを待たずに王宮の外へともたらされていた。
夜陰に紛れて岩城本家の塀を越える者がいた。
それは岩城家が王宮に放っていた間者で、大王の近くに侍っていた内通者から大王崩御の事実を聞いて、その情報を持って来たのだった。その間者はすぐに五条岩城家に向かい、その知らせを伝えた。
蓮がいそいそと伊緒理の邸に向かうために支度をしていた時、父や兄の姿は見なかった。それはいつも通り皆早々に宮廷に出仕したのだと思っていたが、実は夜明け前から活動しており、蓮が起きた時には父は本家へ、兄は宮廷にいたのだった。
蓮は身支度を済ませると、伊緒理と向かい合った。伊緒理も宮廷に向かうための準備を終えていた。二人は抱き合い、口づけした。
「しばらくは会えないだろう。しかし、私の心はあなたの側にある。いつもあなたを思っているよ」
蓮はその言葉を聞いて涙を滲ませた。
「それまでのしばしの別れだ」
伊緒理は名残惜しそうに蓮の顔を見つめ、再び唇を吸った。
New Romantics 第ニ部STAY(STAY GOLD) 第九章4
 小説 STAY(STAY DOLD)
小説 STAY(STAY DOLD)
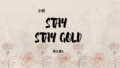
コメント